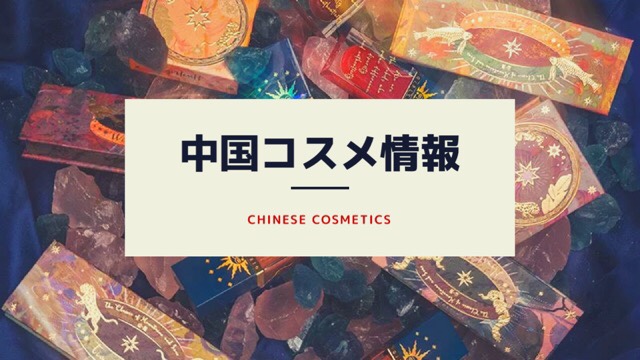こんにちは!リモートガールです。
中国で生活をしていると、日本にいた時に想像していた事と全く異なる事実に直面することが多々あります。
例えば、中国の「タバコ事情」について。
先日の記事「独身の日に次ぐ特大セール「618」で見つけた!今年の注目商品5選」でご紹介した売れ筋商品の中に、日本でも人気の『IQOS』を取り上げました。
日本で中国人転売ヤーを規制する動きがあるほどの人気かつ、中国のECセールでもよく売れているIQOS。
しかしながら、肝心のIQOS利用者を中国で全く見かけないのです。
この七不思議について中国人パートナー協力のもと実情を調査。日本との違いを比較してみました。
日本のタバコ文化
まずは日本でIQOSが急激に普及した経緯を考察してみたいと思います。
前提:日本は喫煙者の肩身が狭い

日本ではタバコを吸わない人を守るという意識のもと、
・喫煙者エリアと非喫煙者エリアの「分煙」
・喫煙所は「個室化」されている
・歩きタバコ、ポイ捨ては「マナー違反」
・「禁煙」エリアが多い
といった施策が取られています。
今でこそもはや当たり前となっていますが、長い年月をかけルールを徹底してきたお陰で、歩道や商業施設で「受動喫煙」をする事無く生活ができているのです。
それでも尚「まだまだ徹底されていない」という声もありますので、これから先もより一層、喫煙者にとって肩身の狭いルールが増えていく事になるのではないでしょうか。
喫煙者は「受動喫煙を軽減する手段」が必要

分煙されているとはいえ、複数人での食事等では非喫煙者との対面は避けられません。
吸わなければいい話なのですが、どうしても我慢できない場合はやはり気を遣う必要が出てくる訳で、そういった場面で吸う側の罪悪感を多少なりとも削減してくれるのがIQOSだったという訳です。
吸っている最中の煙と中に含まれる有害物質、吸った直後の口臭、衣類に付く臭いの削減という観点から見て、接客業に携わる人にとっても好都合。
もちろん、自身の健康面を考えてIQOSに切り替えたという人もいるとは思いますが、あくまでそれは副産物。
爆発的に拡がる理由としては弱いのではないでしょうか。
というのも、日本人の“ある気質”がIQOSの普及に大きく影響していると感じたからです。
日本人は「他人の目を気にする」気質である

良くも悪くも、日本人は他人の目を気にしがちな気質。
良い言い方をすれば「他人の事を配慮している」。
悪い言い方をすれば「他人からの見え方を気にしている」。
日本でのタバコ文化のもとで、これら両方の側面が働く事によって
・アーリーアダプター:非喫煙者に対し少しでも配慮すべくIQOSを取り入れてみる。
↓
・アーリーマジョリティ:IQOSを身の周りの人が使い始めたので気になって使う。
↓
・レイトマジョリティ:周りにIQOS利用を勧められ・誘われたので断れず使う。
といったように、波及していったのではないでしょうか。
結論:日本ではIQOSを使わないと肩身が狭い
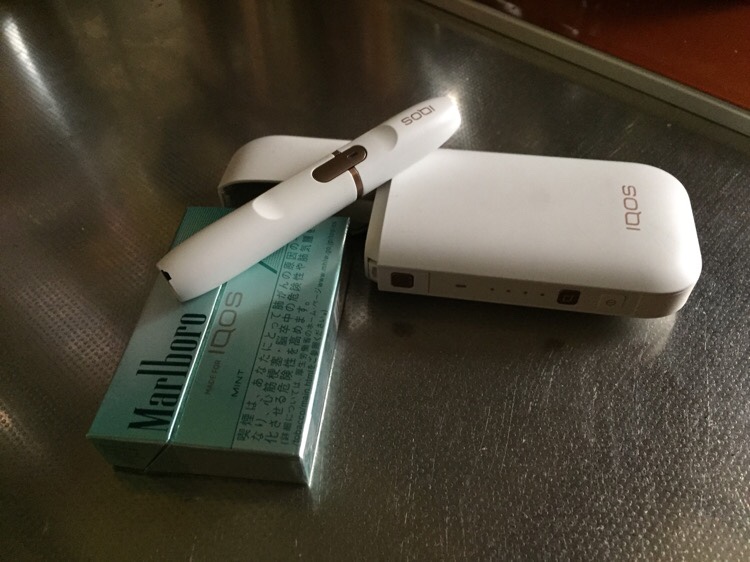
当初は余裕がある人の嗜好品かと思われていたIQOSですが、喫煙者の中での利用者が大多数になるにつれ、普通のタバコを吸っている事が「喫煙者界隈での少数派」となってしまう。
日本での少数派は「悪」といっても過言ではないポジション。
それでなくても日本における喫煙者は肩身が狭いのだから、その中でも更に隅に追いやられるのは辛いというものです。
結果、日本では「IQOS」そのものの性能に惚れ込んで爆発的に浸透した、というよりもIQOSの出現が元来の煙推奨文化の追い風となり使わざるを得ない空気になった。
空気を読んだ、というのが私なりの考察です。
中国のタバコ文化
対して、今度は中国のタバコ文化について。
前提:中国はタバコに関するルールが緩い

中国で歩きタバコは日常茶飯事。道にはあちこちにタバコがポイ捨てされています。
2017年に“世界一厳しい禁煙令”が施行されたと騒がれた上海でさえ、その実情は室内での禁煙に留まるのみで、相変わらず外ではスパスパと歩きタバコをする姿が。
これだけ頻繁に喫煙者と遭遇するにも関わらず、未だ1度もIQOSユーザーに出会ったことがないこの違和感。
一体なぜ、売れているはずのIQOSが全く見かけられないのでしょうか。
中国のタバコ文化を深堀していく内に、その理由が見えてきました。
若年層にとってのハードルが低い

日本に比べると、中国のタバコ価格は安いものから高いものまでその差は大きく、安い物だと1箱50円以下のものも存在します。
更に喫煙に対するルールもあって無いようなもので、法律で許可されている「18歳」以下の少年たちがタバコを買う事も事実上可能です。(誰も気にしない)
街中での喫煙率が高い上に、値段が安く、購入のハードルも低いとなると、若年層の喫煙率が増えるのはごく自然なことだと言えるでしょう。
中国には「敬煙」の文化がある

中国で「タバコ」といえば、ビジネスにおいて「お酒」(地域によっては「お茶」)に並んで重要な役割を果たします。
これは主に男性間のコミュニケーションを円滑にし、ビジネスを促進するために用いられるのですが、その内情は日本の“飲みにケーション”以上にシビアなもの。
例えば、今回リサーチに協力してくれている中国人パートナーの場合。彼は非喫煙者にも関わらず、バックにはいつもライターとタバコを忍ばせています。
理由を聞くと、クライアントとの打合せや食事会での会話よりも、その後の喫煙所こそ真の目的が果たされる場所なんだそう。
そこで勧められたタバコを吸いながら、親交を深めていく。ここで断るのはマナー違反。場合によっては、自分のタバコを相手に勧める必要もある。故に、非喫煙者であってもタバコは必携アイテムなのです。
ここで重要なのは、「手持ちのタバコを相手に勧める」という点。
IQOSではこれができませんよね。(複数人分端末を持っていく根性があれば別ですが)
この勧め合いこそが中国に根付く「敬煙文化」。
お酒とタバコを否が応でも必要とされる中国のビジネスシーンにおいて、男性はなかなかハードですね。
結論:中国でのIQOSは禁煙したい人の為のツール

このように中国ではタバコがビジネスシーンで重要な役割を果たすことから、日本のような「タバコ=悪」という立ち位置に追い込まれることがない、という違いがあります。
敬煙において、相手に勧めるタバコが“普通でない”ものだと何かと面倒だし話が中断されてしまう。そういった面でも、日本のビジネスシーンでの喫煙所とは似て非なるものなのではないでしょうか。
で、肝心のIQOSの行方なのですが、ビジネスシーン・公共の場では見えない部分、つまり各家庭内のみで使用されているという可能性が残ります。
誰にも迷惑を掛けずに思う存分喫煙できる我が家で使うとすれば、その理由はただ1つ。
「禁煙したいから」なのではないでしょうか。
もちろん、家族への受動喫煙も加味してのことでしょうから、家族がいる場所ではIQOSを使うが外では通常のタバコを吸っている、という人もいるでしょう。
- 家族を思って、家ではIQOSを使うが外では普通のタバコを吸う
- 自身の健康面を考え、家ではIQOSを使い、外では吸わない
つまり、この2つの派が中国での見えないIQOSユーザーとして存在しているのではないでしょうか。
見える場所で半強制的に空気を読まされた結果拡がった日本に対し、見えない場所で必要性を感じた人が利用者として増えている中国。
文化の違いはこのような消費の違いをも生み出すものなのですね。
同じ物が同じ用途で消費されるとは限らない

日本では〇〇だから、中国でもきっと〇〇だろう。
そういう思い込みから生まれた「中国で消えるIQOS」という七不思議。
実際は然るべき場所で消費されていた訳で、
『使われ方が異なれば、売り方も変えなければならない。』
こういった小さな違いをキャッチしていくことで、適切な販売戦略を打ち立てることができるのでしょう。
今後もこのような違いを定期的に比較・考察していきたいと思います。
中国ビジネスシーンにおける「男性」のタバコ文化ばかりを取り入れているように見えますが、理由は男女の喫煙率を見れば一目瞭然です。
▼中国の喫煙率
男性:48.4%
女性:1.9%
▼日本の喫煙率
男性:33.7%
女性:11.2%
※2016年統計分のデータ