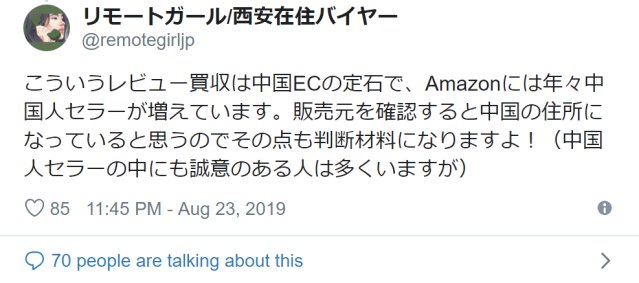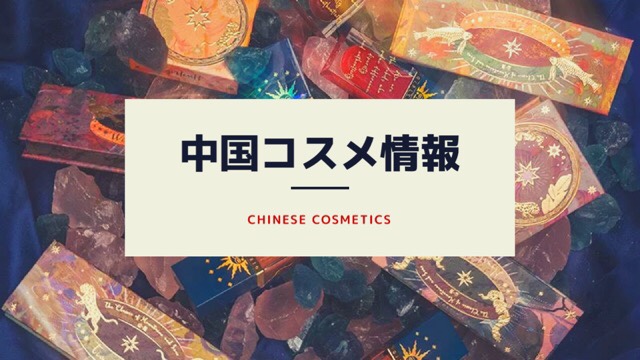先日Twitter上でAmazonのサクラレビューの存在に辟易していた方に、上記のリプライを送ったところ少なからず反響があったので今回は事の発端である「中国ECサイトの実態」と「偽物・粗悪品を避けるための方法」をご紹介します。
「やらせレビュー」がAmazonに大量出現
ドライヤーで高評価356件でトップの商品、詳細で丁寧なレビューばかりなのに星1つが一人だけいて、それ見たら三枚目画像のこれだよ。
業者向けに売り付けるテクニックの講習会あるとは聞いてたけど、これは無法地帯すぎでは pic.twitter.com/ftXfvxKOSy— きづきあきら (@kidukira) August 23, 2019
きっかけはこちらのツイート。
3枚目に表示された画像により「★5点満点のレビューをしてくれたらキャッシュバックする」と謳われた紙が商品に同梱されていることが判明。
道理でレビューが称賛の嵐だった訳だ、と無法状態のAmazonに失望されていました。
リツイート数・いいねの数から判断して、同様の経験がある方も多くいるのでしょう。
「やらせレビュー」の手法は中国で日常茶飯事

中国茶、ゲームソフト、サンドイッチを注文した時に付いてきたキャッシュバックカード
どうもこの手口。中国のニオイがプンプンするぞ…と思い該当する商品をAmazonで検索したところやはり中国企業による販売だと判明。
というのも中国ではECサイトをはじめ、フードデリバリーなどでこのようなキャッシュバックによるやらせレビューを行っている業者がごまんと存在しています。
もはやそれが「悪だ!」と言われる事もなければ、あまりにもやらせレビューが消費者側に周知されすぎているため、そもそもレビュー自体を皆それほど信用していません。
中国ECサイトで偽物・粗悪品を避ける3つの方法

そんな「レビューが意味を為さない」中国ECサイトで買い物をする場合、何を以て商品の良し悪しを判断すれば良いのでしょうか。
以下に私が実践している3つのポイントを挙げてみましたので、順に説明していきます。
中国EC見極めポイント1:京東、天猫を利用する
そもそも商品を購入する場所選びから徹底しよう!という考え方です。
中国の大手ECモールといえば、アリババグループが運営する「タオバオ」が有名ですが、出店ハードルの低さから個人販売者や転売屋が多く介在しており、偽物や粗悪品が多いECモールでもあります。
それであれば、出展基準・審査のハードルが高い「天猫」または「京東」で買い物をすれば良いのです。
これだけで、初期不良や写真と全く違う物が届いたりするリスクを大幅に軽減することができます。
※ただし、これらのECモール内でも「レビュー買収」は行われています。
中国EC見極めポイント2:★5点未満のレビューを参考にする
冒頭に述べたように、いくらレビュー買収が行われていたとしてもそれに屈せず真っ当なレビューをする人が一定数存在します。
レビュー買収は決まって「★5点満点+コメント」を要求しています。
であれば、逆手を取って「★5点未満=買収されていないレビュー」を参考にしましょう。
中国EC見極めポイント3:専門店・メーカー本店から購入する
例えば最近話題の中国コスメを購入する場合。
メーカー名で検索すると大量に同一商品/類似商品が出てきますが、この場合「本店」から購入するのがベストです。
日本であれば薬局のECサイトや他社から購入する事に慣れている(むしろブランド本店から買う人の方が少ないのでは?)と思いますが、中国では必ず本店から購入しましょう。
なぜなら、それ以外の販売者は本物によく似た偽物や類似品である可能性があるからです。
中国人セラー、やらせレビューが増える日本でも応用可能
こういうレビュー買収は中国ECの定石で、Amazonには年々中国人セラーが増えています。販売元を確認すると中国の住所になっていると思うのでその点も判断材料になりますよ!(中国人セラーの中にも誠意のある人は多くいますが)
— リモートガール🇨🇳中国(西安) (@remotegirljp) August 23, 2019
Amazonをはじめとした日本の大手ECモールでは、近年中国企業による販売が増えています。
そこで今回のツイートのような「判断材料」が必要になってきた、という訳です。
私自身中国に住み、中国の優良工場と取引をしている手前、
「中国人セラーを避けよう!」
という言い方はしたくないですし、すべきではないと思うのですが、ルールを守らない割合が圧倒的に多いので半ば致し方なくこのような判断の仕方をしているまでです…。
中国の優良商品を当ブログで積極的に紹介していきます
まだまだ日本に未上陸の中国商品は沢山存在しています。
そういった素晴らしい商品を開発している中国企業については、こちらのブログで積極的に取り上げて紹介していくつもりです。
中国製=悪い!
と頭ごなしに否定するのではなく、消費者側としても正しい知識と判断ができるように、当ブログでも情報を積極的に発信していきたいと思っています。